東京都「すくわくプログラム」実施レポート
- crecerpiano
- 2025年10月29日
- 読了時間: 3分
音の“明るさ”と“暗さ”を感じて、自分の心を見つめる時間
私たちは東京都の「すくわくプログラム」を通じて、都内の保育園にて音楽の外部講師としてたくさんのお子さんたちと「音の探求」をするお手伝いをしております。
10月29日(水)、東京都の「すくわくプログラム」の一環として、都内保育園の5歳児クラスで音楽アウトリーチを行いました。

今回のテーマは 「明るい音と暗い音」
音楽の“調”が変わると、私たちはどんな気持ちになるのか?その感覚を、子どもたちと一緒に「聴く」「感じる」「表す」という3つの体験を通して探りました。
音を感じて、心がひとつになるリズム学習
レッスンのはじめは、緊張をほぐすためのリズムカード遊びから。四分音符・八分音符・二分音符のリズムを体で感じながら手拍子を合わせていきます。すでに継続してリズム学習を行なっているので、息がぴったりあった姿は壮観です。
特に難しい八分音符も、講師の見本をきっかけに思い出して打つことができ、最後には「一緒に音を感じる楽しさ」が教室いっぱいに広がりました。
「音に気持ちはあるの?」聴くことで育つ感性
続いて、サン=サーンス《白鳥》、チャイコフスキー《くるみ割り人形》より「行進曲」、ベートーヴェン《運命》《月光 第1楽章》を聴き比べ、「どんな気持ちになる?」「どんな色が見える?」という問いかけをしました。
子どもたちは音の“明るさ”や“暗さ”を敏感に感じ取り、「怒ってるみたい」「夜の色」「赤の音!」など、自由に表現してくれます。
中でも印象的だったのは、短調の曲を聴いたとき。多くの園児が「黒」「赤」「灰色」と答え、ベートーヴェン《月光》の静かで深い祈りのような響きに、自然と心を寄せているようでした。
音が変わると、絵も変わる
後半は、「キラキラ星」を長調と短調で演奏しながら星の絵を描くワークを行いました。明るい長調を聴きながら描いた星は、黄色く光る夜空。一方、短調では「雲で星が隠れちゃった」「雷が鳴ってる」など、音の印象がそのまま色や形に表れるユニークな作品が並びました。
音を聴いて心が動き、その心の動きが絵に映し出されていく。音楽が“感情を見える形に変える”瞬間を、何度も目の当たりにしました。
音楽で育つ「集中力」と「思いやり」
レッスンの最後は《さんぽ》をみんなで元気に歌い、笑顔で締めくくりました。60分という長い時間にもかかわらず、子どもたちは最後まで集中を切らさず、講師の問いかけにもしっかりと自分の言葉で答える姿が見られました。
小学校入学を半年後に控えた子どもたちが、音楽を通して仲間と呼吸を合わせ、互いを認め合う姿に、「学びの根っこ」が確かに育っていると感じました。
音楽教育の社会的価値 ― “非認知能力”を育てる場として
このプログラムは、単なる音楽の体験ではなく、「聴く・感じる・表す」を通して子どもの感性・共感力・自己表現力を育み、テーマを探求することを目的としています。
音楽を通じて育まれるこれらの力は、近年注目される**非認知能力(思いやり・集中力・創造性)**に直結する要素であり、幼児教育・企業の教育CSR活動の両面で大きな意義を持っています。
CRECER Music Studioでは、こうした感性教育を、企業・自治体・保育施設と連携しながら展開しています。“本物の音”に触れることで、子どもたちは自分の中にある感情を見つめ、それを表現する力を育てていきます。
企業・保育施設担当者の皆さまへ
CRECER Music Studioでは、
幼児期の感性教育・リトミック・鑑賞プログラム
保護者・地域を巻き込んだ音楽イベント
企業の教育CSR・文化貢献プロジェクトとの共同企画
など、目的に応じたオーダーメイドの音楽アウトリーチを実施しています。
音楽が人の心を動かし、コミュニティをつなげる力を、次世代を担う子どもたちの学びの中へ。そのお手伝いを、これからも続けてまいります。


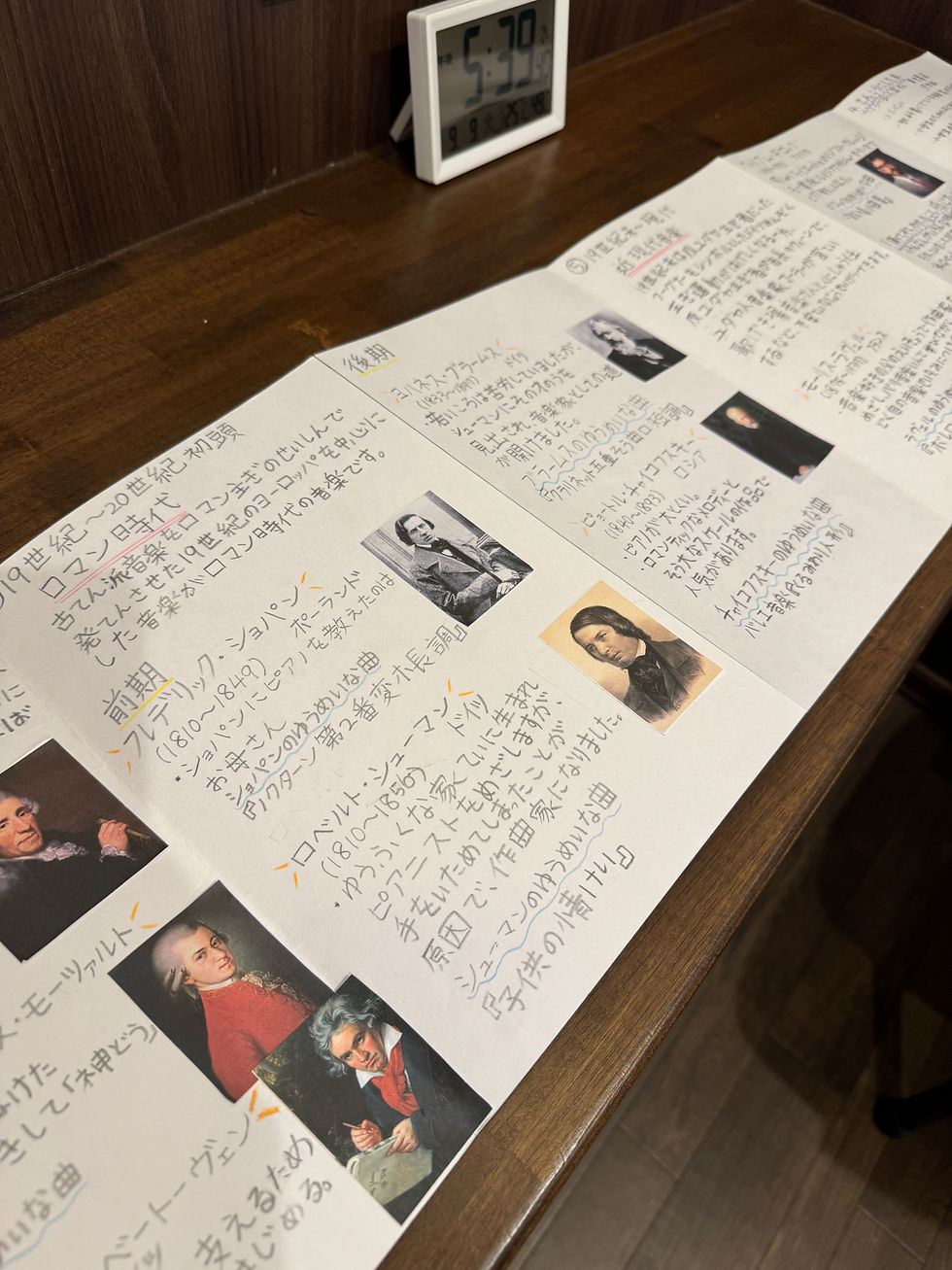
コメント